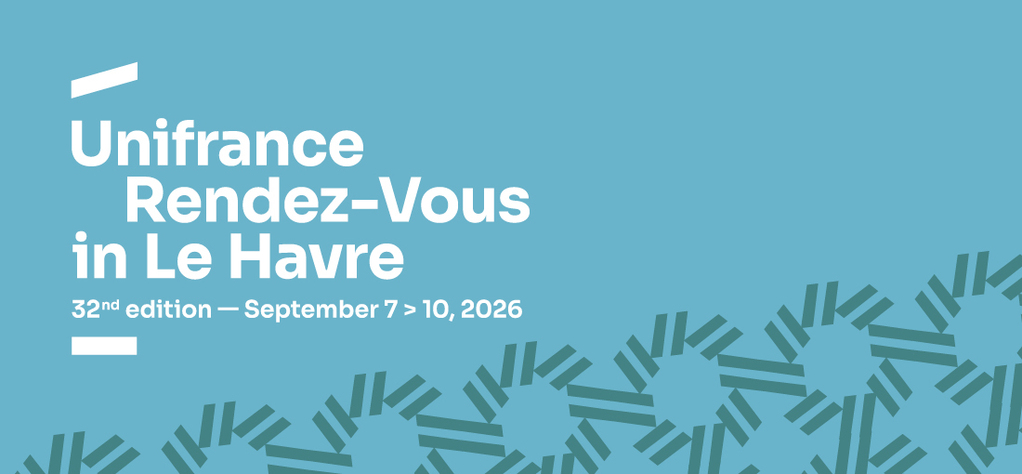『描くべきか、愛を交わすべきか』アルノー&ジャン=マリー・ラリユー監督インタビュー。
人生の一大事をひととおり通過し、残りの生活を雄大な自然の中ではじめた一組の夫婦が、これまで想像さえしなかっためくるめく感性と開放を体験することとなる新感覚のドラマ『 Paint or Make Love 』。監督は2003年のフランス映画祭横浜の『運命のつくり方』が話題となったアルノー( Arnaud Larrieu )とジャン=マリー( Jean-Marie Larrieu )のラリユー兄弟。今年のカンヌ映画祭のコンペティションに出品された最新作をもってまた再び横浜に戻ってきてくれた。
― ストーリーや映画の方向がまったく読めず観ているときは主人公夫婦のように感覚がどんどん開いていくような作品でした。
ジャン=マリー「そういっていただけてうれしいです。「ストーリーの先が読めなかった」と言われることは映画を作っている側からすれば嬉しいことだし、私たちはそういう映画を作りたいと思っているんですよ。」
― 脚本の作業はお二人でどのように進めているんですか?
ジャン=マリー「シノプシスは3,4年前に書いたもの。それからアルノーと一緒にアイデアを出しながら書いています。基本的には二人で書きます。構図やストーリーの作り方にこだわるったり、一方ではセリフにこだわったり、それぞれのこだわるところは違っています。また、一旦撮影に入れば、アルノーはカメラのフレーミングに重点をおいていて、私は俳優との会話に重点を置いています。」
熟年夫婦という設定、感覚の開放というテーマ、大自然の中での生活、など様々な要素が入っている作品ですが、最初のアイデアはどこから生まれましたか?
ジャン・マリー「一番最初に会ったのは、二組のカップルが出会うこと。そのカップルというのは長い間夫婦生活を送ってきたにも関らずそんなにたいした大きなことは起こらず、一人娘も無事一人立ちし、仕事も定年を迎え残りの人生を送ろうとしていた。じゃあ今後の生活でなにが二人に起こるのか、と疑問をもち始めたところで一組のカップルと出会う。それがこの作品のはじまりです。スワッピング(夫婦交換)が描かれるのはそれはあくまで要素。二組のカップルが交流していくなかでたまたま、そういうことが起こってしまった。それが映画の目的ではありません。」
盲目のアダムの存在が作品をひっぱっていっています。視覚の有無だけでなく人間のもつ感覚や感情がすごく繊細に描かれています。
ジャン=マリー「アダムは盲目だけど、見えなくても感じることができ、その分相手の感情にすごく敏感ですよね。また主人公夫婦は彼のお陰で今まで見えていなかったもの、また見たかったものが見えるようになった、ということを描きたかったんです。例えば、マドレーヌをアダムが誘うシーンでは、彼は彼女を見えないけれどしぐさや息遣いによって彼女がそうしたいんだな、ということを感じ取って二人とも自然に上に上がっていってしまう。」
アルノー「私たちも撮影中や編集しているときにはわからなかったけれど、この作品の中でアダムという存在は、主人公夫婦にとって精神分析医のような役割をしていることに気付いていきました。彼らの気付かない、気付かない“ようにしている”欲望に気付かせてあげたのがアダムです。ヨーロッパでは精神分析医というのは基本的にはしゃべらない。患者さんの話を聞くだけ。患者さんは自分のことを全く知らない人間に自分の人生を語ることで何か大事なことをみつけていくんです。「精神分析医とは盲目である」という喩えがあるくらいだしね。」
二組のカップルのキャラクターはどのようにつくっていったんですか?キャスティングは?
アルノー「一番はじめに出来上がったのはマドレーヌです。彼女はこの話のすべてのきっかけをつくっている。キャスティングもすぐにサビーヌ・アゼマ( Sabine Azéma )にお願いしようということで意見がまとまった。彼女もシナリオを読んですぐOKしてくれました。その次は彼女のパートナーを探しました。サビーヌはこれまでに様々な俳優と共演していたけど、ダニエル・オートゥイュ( Daniel Auteuil) とは共演してなかったのでこの二人なら新しいカップルが作れると思いました。彼らも共演したいという意思があったのですぐ話がまとまりました。またアダム役ははじめからセルジ・ロペス( Serge Lopez )にお願いしたいと思っていたんですが、以前出演したドミニク・モル( Dominik Moll )監督の『ハリー、見知らぬ友人( Harry, He Is Here to Help )』と役柄が似ているかな?と心配だったけど実際撮影が進んでキャラクターが出来上がったら全然違うものになったし、やっぱりセルジに演じてもらってよかったと思いました。セルジはスペイン出身の俳優なんですが、エヴァ役のアミラ・カサール( Amira Casar )も日本やイギリスで生活してきた女優。二人ともフランスで活躍している俳優ですが、別の国で育ってきたというところがまたこの役にも合っていたと思います。彼らと出会うことで主人公夫婦の人生は変わっていくのですから、典型的なフランスのカップルというよりは少しギャップがある方がよかったんですよね。」
フランス映画祭横浜には2年前にも『 Un homme, un vrai / 運命のつくりかた 』で参加されていますね。この映画祭をどう思いますか?
アルノー「2年前に来日したとき、また戻ってきたいと思ってました。私たちにとって日本というフランスから離れた国で作品が上映され、そこの観客の反応を見れるのはとても興味深いものです。どういう風に受け入れられるのか実際に見れますし。この作品はすごくフランス的だと思うので特に今回はそう思いますね。」
ジャン=マリー「実際つくり終えた後考えると、今フランス的といいましたが、日本に通じるところも多いんじゃないかと感じました。同じ場所で事が起こって、自然を楽しみ、光があって風景があって・・・。そういう意味では皆さんがどう感じられるか非常に楽しみですね。」
(取材・文:綿野かおり)