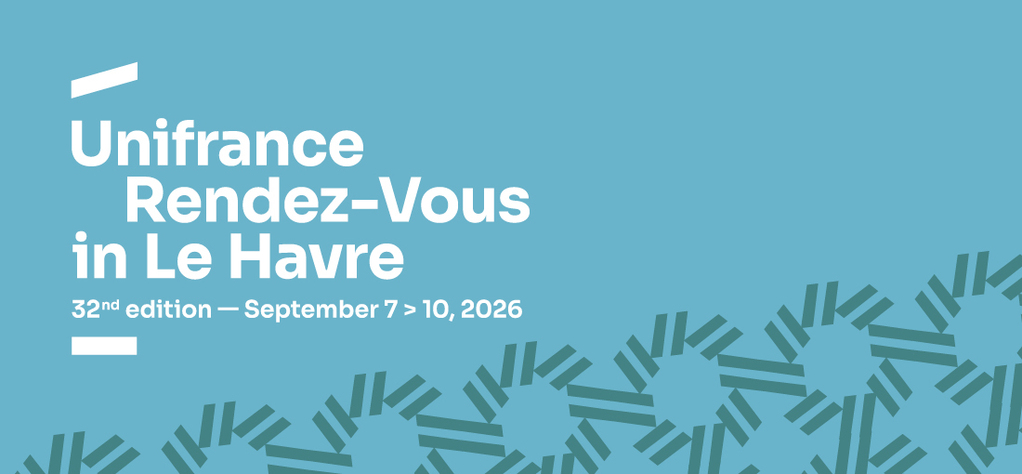『行け、生きろ、生まれ変われ』ラデュ・ミヘイレアニュ監督&主演シラク・M・サバハ:インタビュー。
1984年に行われたエチオピア系ユダヤ人たちのイスラエル移住計画“モーセ作戦”を背景に、深い親子の絆を描いた『行け、生きろ、生まれ変われ/ Va, vis et deviens / 約束の旅路 (公開タイトル)』。ベルリン国際映画祭でも大きな反響を得た本作の監督ラデュ・ミヘイレアニュ( Radu Mihaileanu )と、主演のシラク・M・サバハ( Sirak M. Sabahat )に話を聞いた。
―この作品を撮ることになったいきさつは?
監督「以前、映画祭のためL.A.に行ったとき、エチオピア系ユダヤ人に会ったのがきっかけです。その人は飢えに苦しみ、孤児となったという辛い体験を話してくれましたが、それを聞いた夜は、ずっと涙が止まりませんでした。琴線に触れる体験だったので、モーセ作戦に関する本を読み漁り、イスラエルに実際に赴き、作戦に関わった秘密警察、諜報部員、歴史学者、医師など、多くの人から話を聞きました。こうして行われた5年にわたる調査の結果、書き上げたのが本作です」
― この作品に出演したことはとってどんな意味がありましたか?
サバハ「イスラエルに移住したエチオピア系ユダヤ人として、この作品に出演できたのは光栄なこと。これは自分の民族の物語で、僕自身の人生そのもの。そんな作品に関わるのは、人生の中でもとても重要な体験でした。まずこの作品について知ったとき、とても心を動かされました。自分が抱えてきた感情や経験してきた生き様を、正確に描写してくれていると感じたんです」
― 主人公のシュロモは、ユダヤ人だと偽ることで、飢饉に見舞われたアフリカから脱出し、生き延びるチャンスを手にします。迫害を受け続けてきたユダヤ人の歴史を考えると、かなり皮肉なめぐり合わせのように感じるのですが。
監督「これはユダヤ人だと自分を偽ることで、命を繋ぐ人々を描いた初めての映画だと思います。これまでは、ユダヤ人であることで、死や苦しみ体験してきました。特に第二次世界大戦中はそうでした。でも、この作品は世の中を挑発しようと思って作ったものではありません。自分が感動した、知られざるエチオピア系ユダヤ人たちの物語、普遍的な母と子供の物語を一人でも多くの人に伝えたかっただけ。ですから、映画を作ることが目的だったのではありません。そう考えると、私は語り手であり、映画監督ではないかもしれませんね。多くの人たちが、辛い体験や感情を私と分かち合ってくれましたから、彼らが向けてくれた信頼の深さを思うと、いい加減な仕事はせきませんでした。協力してくれた人々に、“あの作品は失敗したんだ”なんて言うわけにはいきませんからね。ですから、24時間働くこともいとわなかったし、妥協もしませんでした。そして、大きな意味を持つ良い作品に仕上がるよう最大の努力をしたんです。自分にもかなりプレッシャーをかけましたね」
― そんな監督との仕事はどのようなものでしたか?
サバハ「現場は厳しかったけれど、当たりまえのことだと感じていました。
今ではスタッフ、キャストの皆が、監督の姿勢に感謝しています。監督は、私たちの元にやってきて、私たちの物語を語ってくれると言ってくれた。そんな人との仕事なら、例えどんな過酷な現場だったとしても文句の言いようもありませんが」
監督「彼は、撮影がない日もセットに来ていましたよ」
サバハ「この映画に、自分の体験や知識を役立てられるということは名誉なこと。撮影がなくても、現場に行ってアドバイスをすることができて本当に嬉しかった。この映画は、文化を越え、生身の人間同士という立場で、互いに敬意を払うことの大切さを教えてくれる。たとえすぐにではなくても、例え大きいものでなくても、人々の意識の中に何らかの変化を芽生えさせる力があると信じています」
― エチオピア系ユダヤ人については、これまでこのように語られることがなかったのが不思議ですね。
監督「調査のためイスラエルに行ったとき、出会った人たちに、エチオピア人たちについて知っているか尋ねました。すると“ああ、私たちが彼らを救出したんです”と言う。ですから私は、そうではなくて、彼らがどんな生活を余儀なくされて、どんな過酷な体験を強いられてきたかということだと再度問いましたが、知らないと言うんです。でも、この映画を観れば、きっと彼のような人も、道ですれ違うエチオピア人たちを違った目で見ることができる。イスラエルでは今年10月に公開される予定ですが、イスラエル人も知らなかったこの真実を、世界に知らせるのは私の使命のようなもの。誰も語ることのない人々の話を世の中に伝えることに喜びを感じているのです。新しい人に出会い、彼らの人生を思う。私は人間に興味があるんです」
― 撮影中、過去を思い出して感情的になることはありましたか?
サバハ「実はオーディションの時に。はじめ、椅子に座ってセリフを喋っていたのですが、監督から “君はどうして手や顔をやたらと動かすんだ?”と聞かれたんです。そして監督は僕に、椅子の後ろに手を回すように言いました。そのまま再度セリフを口にしたら、涙がどんどんあふれ出てきました。それまでは、自分の心を隠そうとしていて、自分の過去と対峙するようにと監督たちから言われても、“ほっといてくれ”といい続けてきたのですが、今回の体験で、過去を受け止めることができたようです。今ではとても気持ちが楽になり、落ち込んだり、怒りを感じたりすることもなくなりました。まるで、何かのセラピーを受けたように」
監督「彼は心の苦しみを、激しい動きによって隠そうとしていたんです。でも、それをやめさせた時、彼の真の姿を見つけることができました。瞳の中には、悲しみとともに、美しい光も見えました」
― この作品は、あなたのコミュニティの人々はどう受け止めると思いますか。
サバハ「感謝すると確信しています。私の教会の聖職者は、映画を観ていないにも関わらず、監督に敬意を表し、心から信頼しているほどですから」
監督「ベルリン国際映画祭で観たという記者たちが、イスラエルでこの作品について多くを語っていますし、サバハや他の俳優たちもスポークスパーソンとなってくれています。この映画を作って感じた最大の幸福は、映画を通して人々と繋がっていけること。映画には、孤児となった主人公を引き取るフランス系ユダヤ人夫婦が登場しますが、彼らは白人であろうと、黒人であろうと、血が繋がっていようといまいと、深い愛情を子供たちに注ぎます。彼ら以外にも、愛に溢れた親たちが登場しますが、彼らの姿を通して、世の中がいくら複雑な政治事情や矛盾に満ちてはいても、結局は親と子が作りあげている愛に満ちた世界なのだと感じてもらえたら嬉しいです」
(取材・文:牧口じゅん)